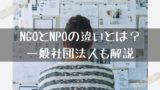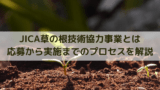この記事は、次のような悩み・疑問を解決します。
- NGO・NPO団体が活動資金を得る方法を知りたい
- 補助金・助成金に応募するための条件が知りたい
- 具体的にどのような補助金・助成金があるのかを知りたい
NGOやNPO団体がどのように活動資金を獲得しているかについては、あまり知られていないかもしれません。
多くの団体は活動資金の大部分が寄付や会費などを占めているようですが、
補助金や助成金などの、NGO・NPO団体をサポートする制度も実は充実しています。
今回は、NPO・NGOの活動資金の獲得方法や、補助金・助成金制度について詳しく解説していきます。
NGO・NPOについて詳しく知りたい方は、こちらの過去の記事もあわせてご覧ください。
NGOやNPO団体が活動資金を得る方法
まず、NGOやNPOが活動資金をどのように得ているのかについて説明していきます。
NGO・NPOの活動資金の獲得方法は大きく5つあります。
① 会費
② 寄付金
③ 事業による収入
④ 補助金・助成金
⑤ 受託事業
① 会費
会費は、その団体の理念や活動に賛同してくれた方々から定期的に得られる収入です。
個人会員や団体会員、賛助会員、マンスリーサポーターなど、様々な名称で設定されており、団体によって制度や金額も異なります。
会員になると特典として、会報誌やメールマガジンなどで情報が受け取れたり、イベントや講演会、セミナーなどの割引を行ったりと、団体によって様々です。
② 寄付金
寄付金は、会費とは違い、団体や活動に賛同してくれた方々から不定期に得られる収入です。
団体の活動全体に対して寄付をいただく場合は自由度が高いですが、ある特定の事業や活動に対する寄付の場合は使途が制限されます。
③ 事業による収入
団体が行う事業によって得られる収入もあります。
事業の具体例を挙げると、講演会やセミナー、スタディツアー、物品や書籍の販売などがあります。
④ 補助金・助成金
補助金・助成金は、主に国や地方自治体、財団などが行っている制度で、
団体の活動や特定の事業に対して、見返りを求めずに金銭をサポートしてくれる制度です。
補助金・助成金については、次の章で代表的なものを紹介します。
⑤ 受託事業
受託事業は、行政や企業などから事業の委託を受けて、その対価としていただく収入のことです。
国際協力NGO・NPO向け補助金・助成金制度5選
次に、国際協力の事業を行っているNGO・NPOが使える、補助金・助成金制度5つとそれぞれの応募条件を紹介します。
外務省・JICAが行っている制度
外務省やJICAが行っている補助金・助成金制度について紹介します。
外務省 NGO事業補助金
外務省のNGO事業補助金は、団体が行う事業にかかる「経費の一部」に対して補助をする制度です。
- 対象となる事業は以下の3つ
ープロジェクトのための調査・評価事業
ー国内の国際協力関連事業
ー国外の国際協力関連事業 - 対象となる経費は、研修会費用、旅費、人件費、事業資料作成・購入費など
- 補助金額は総事業費の1/2以下(ちなみに令和2年度は30~200万円)
- 総事業費が300万円以上の場合は監査が入る
- 見積書や事業計画書を提出し、審査に合格すれば受け取れる
- 法人化を有する(NPO法人、一般社団法人など)
- 法律に基づく事業を実施し,管理する能力を有する
- 政治的,営利的及び宗教的活動を一切行っていない
外務省のNGO事業補助金についてもっと知りたい方はこちらからどうぞ。
外務省 日本NGO連携無償資金協力
同じ外務省の制度でも、日本NGO連携無償資金協力は事業全体にかかる資金を無償で提供する制度です。
したがって対象となる事業や応募条件もかなり制限があります。とくに、活動実績が2年以上求められる点は注意する必要があります。
- 対象となる事業は以下の7つ
1. 開発協力事業
2. NGOパートナーシップ事業
3. リサイクル物資輸送事業
4. 災害等復旧・復興支援事業
5. 地雷・不発弾関係事業
6. マイクロクレジット原資事業
7. 平和構築事業 - いずれも日本のODA政策に沿った事業でなければならない
- 技術協力などのソフト中心の事業は対象としない
- 最大1億円まで供与(詳細はHPを参照)
- 特定非営利活動法人または公益法人として法人登記されている
- 日本のNGOであること
- 国際協力活動が法人の主な目的の一つとなっている
- 法人として少なくとも2年以上にわたり国際協力活動の実績があること
- 非合法的行為・反社会的行為等を行う法人でないこと
- 法人として主務官庁に提出が義務付けられている書類を整備していること
- 事業実施能力や資金管理能力を有していること
外務省の日本NGO連携無償資金協力についてもっと知りたい方はこちらからどうぞ。
JICA 草の根技術協力事業ー支援型ー
JICAの草の根技術協力事業は、その名の通り技術協力に特化した助成制度です。
こちらも、外務省のNGO連携無償資金協力と同じく、事業全体に対して助成する制度となります。
とくに、支援型はこれから本格的な活動を始めたい団体向けのスタートアップの側面もある制度のため、法人化していない任意団体でも活動実績があれば応募できる点が特徴です。
- 対象となる事業の条件は以下の3つ
ー日本の団体が主体的に行う、人を介した「技術協力」である
ー開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に裨益する事業である
ー日本の市民の国際協力への理解・参加を促す機会となる - 1案件につき、3年以内の事業で1,000万円を上限
- 国内外での活動実績を2年以上有し、日本に事務所がある
- 任意団体を含むNGO等の非営利団体、一般社団法人、特定非営利活動法人、大学など
- 団体としての意思決定方法や代表者の権限が明確な組織運営が行われている
- 事業計画および予算策定にあたり適切な会計処理が行われている
- JICA国内拠点による応募前コンサルテーションを受けていること。
JICAの草の根技術協力についてもっと知りたい方はこちらからどうぞ。
企業や財団が行っている制度
つぎに、企業や財団が行っている制度をご紹介します。
Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs
パナソニックが行っている、国際協力活動を行っているNGO・NPOを対象とした基金制度です。
こちらも法人格の必要はなく、組織診断や組織基盤強化からサポートしてくれるため、これから団体として本格的に活動を開始したい団体におすすめです。
- 貧困の解消に向け他のステークホルダーと協働する意欲がある団体に対して、自らの組織基盤強化のために、第三者からの多様で客観的な視点を取り入れた組織診断や組織基盤強化を行うことが目的
- 人材面、事業面、資金面、ガバナンス面などにおいて組織強化
- 1年で200万円が上限
- 活動が「貧困の解消」を目指す SDGs の理念に合致し、意義が高く先駆性や独創性があるかが選考基準の一つ
- 日本国内に主たる事務所があり、民間の非営利組織である
- 新興国・途上国・地域で貧困の解消に向けて取り組んでいる
- 団体の設立から 3 年以上を経過している
- 有給常勤スタッフが 1 名以上である
- 政治、宗教活動を目的とせず、また、反社会的な勢力とは一切関わりがない
パナソニックのNPO/NGOサポートファンドについてもっと知りたい方はこちらからどうぞ

大竹財団助成金事業
こちらは一般社団法人大竹財団が行っている助成金事業です。
この制度の最大の特徴は、年間を通じての募集を行っている点です。したがって、募集時期に合わせて事業を計画するなどの必要がありません。
- 平和、環境/資源エネルギー、人口/社会保障、国際協力を優先分野とする
- 最大50万円の助成
- 申請から可否決定まで1カ月程度
- 公益、社会問題の解決に取りくむ事業をおこなっている
- 日本国内に事務所または連絡先をもつNPO、任意の市民団体、ボランティアグループを対象
大竹財団助成金事業についてもっと知りたい方はこちらからどうぞ。

さいごに
いかがだったでしょうか?
今回は、NGO・NPOの活動資金の獲得方法と活用できる助成金・補助金について解説しました。
基本的に、活動実績が長く、法人化している団体ほど、活動資金を獲得する選択肢は増えていく傾向にありますが、
これから始めようという団体にも、それに見合った制度があるので、うまく活用していけるといいですね。